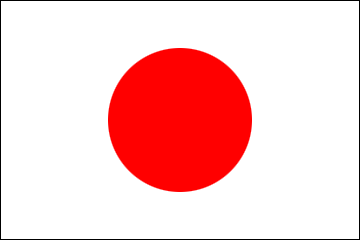日本とグアテマラの関係
令和6年3月25日
1.交流史
2.両国関係の現状
3.経済・技術協力
4.経済関係の現状
5.文化交流
6.在留邦人
1.交流史
(1)日本からグアテマラには、1870年代、岩手県出身の屋須弘平が渡りアンティグア市において写真業を営み、日本の最も古いグアテマラ移民として、またグアテマラの初期の写真家として貴重な記録を多数残している。その後1893年にはハワイでの労働契約を終えた日本人132名がグアテマラに移住したが、これはラ米最初の組織移住と言われている1897年のメキシコ・チアパス州の「榎本移民」に先立つこと4年であった。その後これらの移住者たちは、劣悪な労働条件等に悩まされ、メキシコに逃れた者もあり、後続の移住者もなかったため、グアテマラ移住はそれ以上の進展を遂げることはなかった。
(2)日本・グアテマラ外交関係は、1935年(昭和10年)2月20日、在メキシコ日本国公使のグアテマラ兼任公使任命をもって始まり、同年グアテマラ側は在中華民国大使を日本兼任公使に任命した。1941年12月8日、日米開戦と同時にグアテマラは対日宣戦し外交関係は中断されたが、1954年9月23日、サン・フランシスコ条約署名により再開された。1955年7月1日、日本は在メキシコ大使をグアテマラ兼任公使に任命した。 グアテマラ側は戦後、駐日公使を長らく任命しなかったが、1964年3月20日付けで相互に大使館に昇格させたのに続き、同年11月21日、東京にグアテマラ大使館を開設し、日本側も1967年1月27日在グアテマラ大使館実館を設置し現在に至っている。2020年2月には、外交関係樹立85周年を迎えた。
2.両国関係の現状
(1)日本はグアテマラに対する二国間援助の主要供与国の1つとなっていることもあり、両国関係も経済技術協力が中心となっている。1996年末の最終和平協定署名以降、我が国の援助は和平プロセスの支援に重点を置き、更に現在は持続可能な社会・経済開発への支援に努めている。
(2)ポルティージョ大統領(2001年)以降、ベルシェ大統領(2005年)、コロン大統領(2010年)、モラレス大統領(2019年)の歴代大統領の訪日が実現。2016年のモラレス政権発足後では、2016年11月、モラレス・モンロイ経済大臣、2019年3月のホベル外務大臣、同年10月にモラレス大統領(即位の礼参列)が訪日。我が国からは2012年に山根外務副大臣、2013年に谷川文部科学副大臣、2015年宇都外務大臣政務官、2017年岡本外務大臣政務官、2019年に佐藤外務副大臣、2021年に茂木敏充外務大臣が来訪している。
(3)1987年の「青年海外協力隊派遣取極」以降、グアテマラへのJICA海外協力隊(JOCV)派遣者数は着実に伸びているおり、累計800名を越える。通年、20名程度のJOCVがグアテマラで活躍し、保健衛生、教育、環境、観光業、農村開発、スポーツ等幅広い分野でグアテマラ社会に貢献している。2020年からの当国におけるコロナウイルス感染拡大の影響を受け、JOCV派遣が一時中断されたが、2022年に再開した。
(4)2014年9月30日から10月3日にかけて、秋篠宮同妃両殿下が日本との友好親善関係の強化に向けてグアテマラを御訪問された。両殿下は1日、ペレス・モリーナ大統領、ロサ・レアル・デ・ペレス大統領夫人への表敬、同大統領夫妻主催の晩餐会に出席された他、2日にはティカル国立公園、3日にはアンティグア市を御訪問された。日本の皇族のグアテマラ御訪問は1997年の常陸宮同妃両殿下の御訪問に次いで2回目、秋篠宮同妃両殿下にとっては初のグアテマラ御訪問となった。
(5)これまでの日本・グアテマラ間の要人往来は次の通り。
ア 日本の要人のグアテマラ訪問
イ グアテマラ要人の訪日
(1)日本の対グアテマラ二国間ODA実績は、1995年には米国を抜いて第1位となり(37.1百万ドル)、2000年まで6年連続で第1位であった。2019-20年(年平均)の日本の援助額は32.7百万ドル、第2位(国際機関・マルチ支援除く)で主要ドナー国の対グアテマラ援助総額(552.2百万ドル)の約5.92%を占める。なお、同年におけるODA実績(国際機関等含む)第1位は米国(169.4百万ドル)、第2位は米州開発銀行(150.5百万米ドル)、第3位EU関連機関(37.7百万ドル)、続いて第4位日本となっている(出典:OECD―DAC、支出純額ベース)。
(2)中米最大の人口とGDPを有するグアテマラは、1996年の内戦終結以降、平和と民主主義の定着および地方と都市部における格差の是正に努めてきたが、貧困率および貧困の地域・民族間格差は依然として大きく、人間開発指数(2020年)は、中南米・カリブ地域でハイチ、ホンジュラス、ニカラグアに次いで低い(189カ国中127位)。また、ハリケーン、地震、火山噴火などの災害に度々見舞われており、特に近年は気候変動の影響による洪水、土砂災害が多発し、自然災害に対する脆弱性の改善が持続的発展の観点から大きな課題となっている。
(3)我が国は、グアテマラとの間で1977年に技術協力協定を締結し、1984年から研修の受入れを開始。1987年に締結された青年海外協力隊派遣取極に基づき、1989年からJICA海外協力隊の派遣を開始している。その後、1996年12月29日、36年続いた中米最後の内戦に終止符が打たれたことを受け、1997年1月、ブリュッセルにおいてIDB主催の対グアテマラ支援国会合が開催され、IDB、世銀を始め、日本を含む各国ドナー間で、全てに優先して和平協定履行のための支援を重視するべきとのコンセンサスが得られた。以降、教育、保健・衛生、インフラ整備、治安等の分野を重点分野とし、無償資金協力を中心に支援を実施してきている。
(4)2004年、JICA海外協力隊の当国における貢献が評価されケツァル勲章を叙勲した。また、2005年には熱帯性低気圧「スタン」、2010年には熱帯暴風雨「アガサ」、2012年にはグアテマラ西部大地震、2018年にはフエゴ火山噴火、2020年には熱帯低気圧「イータ」、「イオタ」が発生したことを受け、日本は、それぞれの自然災害に対し緊急援助を実施。2020年以降は新型コロナウイルス感染症の蔓延対策支援としてコールド・チェーンの強化を含む保健・医療の整備実施を目的とした救急車や医療機材、保冷機材等の供与や医療関係者を対象とした研修を行った。また、近年、中米各国では、米国を目指す移民の増加、またそれに伴う治安の悪化が懸念されており、移民発生の要因の一つである貧困の改善が喫緊の課題となっているため、移民対策支援も行っている。 2023年には技術協力協定締結45周年、2025 年には日・グアテマラ外交関係樹立90周年を迎える中、日本は、引き続きグアテマラの持続可能な社会・経済開発に向けた支援を行っている。
4.経済関係の現状
(1) 進出企業:進出企業:24社
(2) 日本からグアテマラへ向けた輸出(373百万ドル、2021年中銀)は、主に自動車、鉄銅、一般機械、電子機械。輸入は、コーヒー、胡麻、砂糖等。
(3) グアテマラ産コーヒー、日本市場で健闘:2004年9月、日本で発売された「レインボーマウンテン(ボス缶)」は、サントリーとグアテマラ全国コーヒー協会(ANACAFE)がタイアップして発売。2004年の発売後10年間で、累計販売本数が 33億本を越えるロングセラー商品となっている。
(4)日本車メーカー、グアテマラ市場で優位:2021年、グアテマラの新車販売は、年間22、401台に達し、日本車メーカーの販売台数は新車・メーカー別で、トヨタ、マツダ、日産、ホンダ、三菱、いすゞ、スズキ、日野が売れ筋としてトップ10入り(2014年から2021年の累計販売)。日本車は、2021年、新車市場では60.1%を売り上げた。
5.文化交流
(1)当館は、グアテマラ側官民関係機関・団体および国際交流基金の協力を得て、日本芸術・文化公演や各種展示会、講演会等を通じた日本文化紹介事業を実施してきている。これら文化事業は首都にとどまらず、ケツァルテナンゴやウエウエテナンゴ、チキムラといった地方都市でも開催してきており、グアテマラ国民全体に日本文化の素晴らしさを伝えるための情報発信を行ってきている。また、当館が主催する行事以外にも、地方自治体、大学、博物館、美術館などの学術機関、草の根レベルの日本文化団体(そろばん、合気道、剣道、盆栽、アニメなど)と良好な関係を構築し、文化行事を共催したり側面支援を行ったりすることによって、有機的に連携して日本文化を発信してきている。
(2)2017年、私立バジェ大学開発チームによる人工衛星プロジェクトが宇宙航空研究開発機構(JAXA)および 国連宇宙部(UNOOSA)の連携協力による第2回Cube SATプロジェクトに選出され、グアテマラ初の小型人工衛星となった「ケツァル1」は、2020年3月に米国フロリダ州のケネディ宇宙センターから国際宇宙ステーション(ISS)日本実験棟「きぼう」へ打ち上げられ、同年4月28日、「きぼう」から宇宙空間に放出された。
その後、宇宙でのさまざまな情報収集というミッションを遂行した(2021年1月にミッション終了)。
(3)2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会においてグアテマラ代表団として26人アスリート(オリンピック24名、パラリンピック2名)が東京大会に参加。男子バトミントンのケビン・コルドン選手が4位入賞、男子競泳100メートル・バタフライでルイス・マルティネス選手が8位入賞、男子5000メートルでルイス・グリハルバ選手が決勝進出する等活躍した。
奈良県田原本町および北海道恵庭市がグアテマラのホストタウンとなった。恵庭市ではグアテマラ競歩競技選手団の事前合宿を実施、田原本町においても2020年に交流事業、新型コロナウイルス対策のマスクの寄付を町民に募り、同年グアテマラ市において引き渡し、また、オリパラ後もグアテマラ選手団とオンラインで交流を行う等、競技以外でもオリンピック・パラリンピックを機にスポーツを通じた交流が実現した。
(4)日本語教育においては、1992年から2012年まで国立サン・カルロス大学附属言語センター(CALUSAC)へJICA海外協力隊員(日本語教師)を派遣してきたほか、国際交流基金のスキームを活用し日本語教材の供与、日本語教師の本邦研修派遣を行っている。なお、2021年CALUSACは長年の日本語学習を通じた日グアテマラ両国の相互理解や友好親善に寄与したことを評価され外務大臣表彰を受賞した。また、同センターとは、当館との共催で毎年「日本語弁論大会」を開催しており、同大会の成績優秀者を日本へ招へいし、対日理解を深める事業を実施している。このほか、数は少ないながら、私立大学や私設語学学校においても日本語教育が行われている。
(5)文部科学省国費留学生制度により、これまで多くの人のグアテマラ人が研究生、学部生、専修生、教員研修生として日本へ留学し、留学後もそれぞれの日本留学経験を活かし活躍している。
(6)両国間の文化交流・相互理解促進に貢献した功績を称え、これまで以下の叙勲・表彰を実施している。
6.在留邦人
(1)在留邦人:2022年6月現在の当国在住の在留邦人は284名であり、そのうち126名が永住者である他は、大使館、JICA海外協力隊、JICA等の経済協力プロジェクト、日本企業等の長期滞在者となっている。
(2)日本人学校:グアテマラ日本人学校は1977年(昭和52年)に設置された。2021年(令和3年)3月末に閉校。
2.両国関係の現状
3.経済・技術協力
4.経済関係の現状
5.文化交流
6.在留邦人
1.交流史
(1)日本からグアテマラには、1870年代、岩手県出身の屋須弘平が渡りアンティグア市において写真業を営み、日本の最も古いグアテマラ移民として、またグアテマラの初期の写真家として貴重な記録を多数残している。その後1893年にはハワイでの労働契約を終えた日本人132名がグアテマラに移住したが、これはラ米最初の組織移住と言われている1897年のメキシコ・チアパス州の「榎本移民」に先立つこと4年であった。その後これらの移住者たちは、劣悪な労働条件等に悩まされ、メキシコに逃れた者もあり、後続の移住者もなかったため、グアテマラ移住はそれ以上の進展を遂げることはなかった。
(2)日本・グアテマラ外交関係は、1935年(昭和10年)2月20日、在メキシコ日本国公使のグアテマラ兼任公使任命をもって始まり、同年グアテマラ側は在中華民国大使を日本兼任公使に任命した。1941年12月8日、日米開戦と同時にグアテマラは対日宣戦し外交関係は中断されたが、1954年9月23日、サン・フランシスコ条約署名により再開された。1955年7月1日、日本は在メキシコ大使をグアテマラ兼任公使に任命した。 グアテマラ側は戦後、駐日公使を長らく任命しなかったが、1964年3月20日付けで相互に大使館に昇格させたのに続き、同年11月21日、東京にグアテマラ大使館を開設し、日本側も1967年1月27日在グアテマラ大使館実館を設置し現在に至っている。2020年2月には、外交関係樹立85周年を迎えた。
2.両国関係の現状
(1)日本はグアテマラに対する二国間援助の主要供与国の1つとなっていることもあり、両国関係も経済技術協力が中心となっている。1996年末の最終和平協定署名以降、我が国の援助は和平プロセスの支援に重点を置き、更に現在は持続可能な社会・経済開発への支援に努めている。
(2)ポルティージョ大統領(2001年)以降、ベルシェ大統領(2005年)、コロン大統領(2010年)、モラレス大統領(2019年)の歴代大統領の訪日が実現。2016年のモラレス政権発足後では、2016年11月、モラレス・モンロイ経済大臣、2019年3月のホベル外務大臣、同年10月にモラレス大統領(即位の礼参列)が訪日。我が国からは2012年に山根外務副大臣、2013年に谷川文部科学副大臣、2015年宇都外務大臣政務官、2017年岡本外務大臣政務官、2019年に佐藤外務副大臣、2021年に茂木敏充外務大臣が来訪している。
(3)1987年の「青年海外協力隊派遣取極」以降、グアテマラへのJICA海外協力隊(JOCV)派遣者数は着実に伸びているおり、累計800名を越える。通年、20名程度のJOCVがグアテマラで活躍し、保健衛生、教育、環境、観光業、農村開発、スポーツ等幅広い分野でグアテマラ社会に貢献している。2020年からの当国におけるコロナウイルス感染拡大の影響を受け、JOCV派遣が一時中断されたが、2022年に再開した。
(4)2014年9月30日から10月3日にかけて、秋篠宮同妃両殿下が日本との友好親善関係の強化に向けてグアテマラを御訪問された。両殿下は1日、ペレス・モリーナ大統領、ロサ・レアル・デ・ペレス大統領夫人への表敬、同大統領夫妻主催の晩餐会に出席された他、2日にはティカル国立公園、3日にはアンティグア市を御訪問された。日本の皇族のグアテマラ御訪問は1997年の常陸宮同妃両殿下の御訪問に次いで2回目、秋篠宮同妃両殿下にとっては初のグアテマラ御訪問となった。
(5)これまでの日本・グアテマラ間の要人往来は次の通り。
ア 日本の要人のグアテマラ訪問
| 1987年 9月 | 倉成外務大臣 |
| 1989年 7月 | 田中直紀外務政務次官 |
| 1991年 1月 | 小渕恵三特派大使(大統領就任式典) |
| 1991年10月 | 鈴木宗男外務政務次官 |
| 1992年 9月 | 衆議院友好親善議員団(団長:小渕恵三議員) |
| 1993年10月 | 東外務政務次官 |
| 1994年 2月 | 今津寛衆議院議員 |
| 1996年 1月 | 山口 鶴男特派大使(大統領就任式典) |
| 1996年12月 | 村山比佐斗特派大使(最終和平協定署名式典) |
| 1997年 9月 | 常陸宮同妃両殿下 |
| 2000年 1月 | 近江巳記夫特派大使(大統領就任式典) |
| 2001年 8月 | 山口泰明外務大臣政務官 |
| 2004年 1月 | 森山真弓特派大使(大統領就任式典) |
| 2005年 2月 | 小野寺五典外務大臣政務官(日・中米交流年記念式典) |
| 2006年 5月 | 土屋品子衆議院議員 |
| 2007年 3月 | 田中和徳財務副大臣(IDB年次総会) |
| 2007年 8月 | 横路衆議院副議長 |
| 2008年 1月 | 山口泰明特派大使(大統領就任式) |
| 2010年12月 | 山花郁夫外務大臣政務官 |
| 2012年 1月 | 山根隆治外務副大臣 |
| 2013年 5月 | 谷川文部科学副大臣 |
| 2014年 7月 | 望月衆議院議員、西村衆議院議員 |
| 2014年 9月 | 秋篠宮同妃両殿下 |
| 2015年 5月 | 宇都隆史外務大臣政務官 |
| 2017年 7月 | 中川正春衆議院議員、渡辺周衆議院議員、白眞勲参議院議員(北朝鮮の難民と人権に関する国際議員連盟(IPCNKR)年次総会) |
| 2017年12月 | 岡本三成外務大臣政務官 |
| 2019年 9月 | 佐藤正久外務副大臣 |
| 2020年 1月 | 山口泰明特派大使(大統領就任式) |
| 2021年7月 | 茂木敏充外務大臣 |
| 2024年 1月 | 穂坂泰特派大使(大統領就任式) |
イ グアテマラ要人の訪日
| 1990年11月 | リベ-ラ外務大臣(即位の礼参列) |
| 1991年 4月 | リナ-レス中銀総裁(IDB名古屋総会出席) |
| 1991年 6月 | シェカヴィサ経済企画庁長官 |
| 1991年 9月 | グアテマラ国会議員団(衆議院招待) |
| 1992年 2月 | フェンテン経済企画庁長官 |
| 1993年12月 | コ-エン外務次官 |
| 1994年12月 | デル・バジェ農牧食糧大臣 |
| 1996年 7月 | ステイン外相(日・中米フォーラム出席) |
| 1998年 2月 | アギレラ外務次官(政治担当)(中堅指導者招聘計画による訪日) |
| 1999年 8月 | ヒメネス外務次官(経済担当)(日・中米フォーラム出席) |
| 2001年 5月 | ポルティージョ大統領、オレジャーナ外相 |
| 2001年 9月 | クアン観光庁長官 |
| 2002年 2月 | レジェス副大統領、ウェイマン大蔵大臣、アギレラ和平庁長官 |
| 2002年 3月 | オルドーニェス外務次官(日・中米フォーラム出席) |
| 2002年 5月 | デ・ラモス通信運輸公共事業大臣 |
| 2002年11月 | アルチラエネルギー・鉱山大臣(日・中米インフォメーション・エンカウンター出席) |
| 2003年 3月 | デ・レジェス副大統領、デ・コティ文化大臣(マヤ展開会式出席) |
| 2003年 3月 | カセレス環境大臣(第3回世界水フォーラム出席) |
| 2003年 5月 | デ・ラモス通信運輸公共事業大臣 |
| 2003年 9月 | セッツ農牧大臣(食糧増産援助入札立ち会い) |
| 2003年12月 | モラレス人権擁護官(中堅指導者招聘による訪日) |
| 2004年 4月 | ダリィ環境大臣(第2回地球観測サミット出席) |
| 2004年 4月 | マルティネス外務次官(「愛・地球博」中米共同館関連会合出席) |
| 2004年10月 | モンテホ和平庁長官(中堅指導者招聘計画による訪日) |
| マルティネス外務次官(日・中米フォーラム出席) | |
| 2004年12月 | フェルナンデス国会議員(国民希望党) |
| 2005年 4月 | デ・ボニージャ蔵相(IDB沖縄年次総会) |
| 2005年 8月 | ベルシェ大統領、ブリッツ外務大臣他(日本・中米首脳会談) |
| 2006年 2月 | ブリッツ外務大臣 |
| 2006年 3月 | ノルマ・キシュタン和平庁長官 |
| 2006年 9月 | アセーニャ教育大臣(第3回科学技術関係閣僚会合出席) |
| 2007年 7月 | マテウ文化スポーツ大臣(インカ、マヤ、アステカ展開会式) |
| 2007年10月 | アセーニャ教育大臣(第4回科学技術関係閣僚会合出席) |
| 2007年12月 | エスコベド国民希望党外交顧問(21世紀パートナーシップ促進招聘) |
| 2008年10月 | ピラ外務次官(IDB主催アジア・LAC貿易投資フォーラム) |
| 2009年10月 | エスパーダ副大統領(第6回科学技術(STS)フォーラム) |
| 2010年 3月 | フェラテ環境天然資源大臣(国連持続可能な廃棄物管理準備会合) |
| 2010年10月 | コロン大統領(実務訪問賓客、外交関係樹立75周年。ロダス外務大臣同行) |
| 2011年 7月 | マルドナド外務次官(日・中米フォーラム) |
| 2011年 9月 | エスコベド文化スポーツ大臣 |
| 2012年 5月 | カバジェロス外務大臣(外務省賓客) |
| 2013年 7月 | エスピノサ外務次官(日・中米フォーラム) |
| 2015年 3月 | パディージャ通信監督庁長官 |
| 2016年11月 | モラレス・モンロイ経済大臣(IDB主催日本・ラ米ビジネス・フォーラム出席) |
| 2019年 3月 | サンドラ・ホベル外務大臣(第5回国際女性会議WAW!/W20出席) |
| 2019年10月 | モラレス大統領(即位の礼) |
| 2024年 3月 | オロスコ・ペレス外務次官 |
| 2024年 5月 | マルティネス外務大臣 |
| 2025年 6月 | アレバロ大統領 |
(6)日本・グアテマラ間の条約・協定関係
3.経済・技術協力1971年 貿易上の待遇供与に関する取極
1976年 査証免除取極
1977年 技術協力協定
1987年 青年海外協力隊派遣取極
(1)日本の対グアテマラ二国間ODA実績は、1995年には米国を抜いて第1位となり(37.1百万ドル)、2000年まで6年連続で第1位であった。2019-20年(年平均)の日本の援助額は32.7百万ドル、第2位(国際機関・マルチ支援除く)で主要ドナー国の対グアテマラ援助総額(552.2百万ドル)の約5.92%を占める。なお、同年におけるODA実績(国際機関等含む)第1位は米国(169.4百万ドル)、第2位は米州開発銀行(150.5百万米ドル)、第3位EU関連機関(37.7百万ドル)、続いて第4位日本となっている(出典:OECD―DAC、支出純額ベース)。
(2)中米最大の人口とGDPを有するグアテマラは、1996年の内戦終結以降、平和と民主主義の定着および地方と都市部における格差の是正に努めてきたが、貧困率および貧困の地域・民族間格差は依然として大きく、人間開発指数(2020年)は、中南米・カリブ地域でハイチ、ホンジュラス、ニカラグアに次いで低い(189カ国中127位)。また、ハリケーン、地震、火山噴火などの災害に度々見舞われており、特に近年は気候変動の影響による洪水、土砂災害が多発し、自然災害に対する脆弱性の改善が持続的発展の観点から大きな課題となっている。
(3)我が国は、グアテマラとの間で1977年に技術協力協定を締結し、1984年から研修の受入れを開始。1987年に締結された青年海外協力隊派遣取極に基づき、1989年からJICA海外協力隊の派遣を開始している。その後、1996年12月29日、36年続いた中米最後の内戦に終止符が打たれたことを受け、1997年1月、ブリュッセルにおいてIDB主催の対グアテマラ支援国会合が開催され、IDB、世銀を始め、日本を含む各国ドナー間で、全てに優先して和平協定履行のための支援を重視するべきとのコンセンサスが得られた。以降、教育、保健・衛生、インフラ整備、治安等の分野を重点分野とし、無償資金協力を中心に支援を実施してきている。
(4)2004年、JICA海外協力隊の当国における貢献が評価されケツァル勲章を叙勲した。また、2005年には熱帯性低気圧「スタン」、2010年には熱帯暴風雨「アガサ」、2012年にはグアテマラ西部大地震、2018年にはフエゴ火山噴火、2020年には熱帯低気圧「イータ」、「イオタ」が発生したことを受け、日本は、それぞれの自然災害に対し緊急援助を実施。2020年以降は新型コロナウイルス感染症の蔓延対策支援としてコールド・チェーンの強化を含む保健・医療の整備実施を目的とした救急車や医療機材、保冷機材等の供与や医療関係者を対象とした研修を行った。また、近年、中米各国では、米国を目指す移民の増加、またそれに伴う治安の悪化が懸念されており、移民発生の要因の一つである貧困の改善が喫緊の課題となっているため、移民対策支援も行っている。 2023年には技術協力協定締結45周年、2025 年には日・グアテマラ外交関係樹立90周年を迎える中、日本は、引き続きグアテマラの持続可能な社会・経済開発に向けた支援を行っている。
4.経済関係の現状
(1) 進出企業:進出企業:24社
(2) 日本からグアテマラへ向けた輸出(373百万ドル、2021年中銀)は、主に自動車、鉄銅、一般機械、電子機械。輸入は、コーヒー、胡麻、砂糖等。
(3) グアテマラ産コーヒー、日本市場で健闘:2004年9月、日本で発売された「レインボーマウンテン(ボス缶)」は、サントリーとグアテマラ全国コーヒー協会(ANACAFE)がタイアップして発売。2004年の発売後10年間で、累計販売本数が 33億本を越えるロングセラー商品となっている。
(4)日本車メーカー、グアテマラ市場で優位:2021年、グアテマラの新車販売は、年間22、401台に達し、日本車メーカーの販売台数は新車・メーカー別で、トヨタ、マツダ、日産、ホンダ、三菱、いすゞ、スズキ、日野が売れ筋としてトップ10入り(2014年から2021年の累計販売)。日本車は、2021年、新車市場では60.1%を売り上げた。
5.文化交流
(1)当館は、グアテマラ側官民関係機関・団体および国際交流基金の協力を得て、日本芸術・文化公演や各種展示会、講演会等を通じた日本文化紹介事業を実施してきている。これら文化事業は首都にとどまらず、ケツァルテナンゴやウエウエテナンゴ、チキムラといった地方都市でも開催してきており、グアテマラ国民全体に日本文化の素晴らしさを伝えるための情報発信を行ってきている。また、当館が主催する行事以外にも、地方自治体、大学、博物館、美術館などの学術機関、草の根レベルの日本文化団体(そろばん、合気道、剣道、盆栽、アニメなど)と良好な関係を構築し、文化行事を共催したり側面支援を行ったりすることによって、有機的に連携して日本文化を発信してきている。
(2)2017年、私立バジェ大学開発チームによる人工衛星プロジェクトが宇宙航空研究開発機構(JAXA)および 国連宇宙部(UNOOSA)の連携協力による第2回Cube SATプロジェクトに選出され、グアテマラ初の小型人工衛星となった「ケツァル1」は、2020年3月に米国フロリダ州のケネディ宇宙センターから国際宇宙ステーション(ISS)日本実験棟「きぼう」へ打ち上げられ、同年4月28日、「きぼう」から宇宙空間に放出された。
その後、宇宙でのさまざまな情報収集というミッションを遂行した(2021年1月にミッション終了)。
(3)2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会においてグアテマラ代表団として26人アスリート(オリンピック24名、パラリンピック2名)が東京大会に参加。男子バトミントンのケビン・コルドン選手が4位入賞、男子競泳100メートル・バタフライでルイス・マルティネス選手が8位入賞、男子5000メートルでルイス・グリハルバ選手が決勝進出する等活躍した。
奈良県田原本町および北海道恵庭市がグアテマラのホストタウンとなった。恵庭市ではグアテマラ競歩競技選手団の事前合宿を実施、田原本町においても2020年に交流事業、新型コロナウイルス対策のマスクの寄付を町民に募り、同年グアテマラ市において引き渡し、また、オリパラ後もグアテマラ選手団とオンラインで交流を行う等、競技以外でもオリンピック・パラリンピックを機にスポーツを通じた交流が実現した。
(4)日本語教育においては、1992年から2012年まで国立サン・カルロス大学附属言語センター(CALUSAC)へJICA海外協力隊員(日本語教師)を派遣してきたほか、国際交流基金のスキームを活用し日本語教材の供与、日本語教師の本邦研修派遣を行っている。なお、2021年CALUSACは長年の日本語学習を通じた日グアテマラ両国の相互理解や友好親善に寄与したことを評価され外務大臣表彰を受賞した。また、同センターとは、当館との共催で毎年「日本語弁論大会」を開催しており、同大会の成績優秀者を日本へ招へいし、対日理解を深める事業を実施している。このほか、数は少ないながら、私立大学や私設語学学校においても日本語教育が行われている。
(5)文部科学省国費留学生制度により、これまで多くの人のグアテマラ人が研究生、学部生、専修生、教員研修生として日本へ留学し、留学後もそれぞれの日本留学経験を活かし活躍している。
(6)両国間の文化交流・相互理解促進に貢献した功績を称え、これまで以下の叙勲・表彰を実施している。
| ア | 2011 | ホルヘ・サルミエントス氏(故) 旭日小綬章(「ヒロシマのピカ」作曲など) |
| イ | 2011 | 兒嶋英雄氏 外務大臣表彰(当国における染色技術普及) |
| ウ | 2013 | キラ・アブレウ氏 在外公館長表彰(そろばんを通じた日本文化普及) |
| エ | 2014 | 国立サン・カルロス大学言語センター(CALUSAC) 在外公館長表彰(日本語普及) |
| オ | 2014 | 河澄さつき氏 在外公館長表彰(当国における算数普及) |
| カ | 2015 | 中村誠一 金沢大学教授 在外公館長表彰(当国マヤ遺跡の保存研究に貢献) |
| キ | 2015 | カルロス・リーベルス氏 在外公館長表彰(法律分野での貢献) |
| ク | 2016 | グレンダ・マルティネス氏 在外公館長表彰(JICA帰国研修員の会会長、日本文化普及に貢献) |
| ケ | 2017 | キラ・リスクティン・デ・アブレウ氏 外務大臣表彰(そろばんを通じた日本文化普及) |
| ソ | 2018 | ダニーロ・シエカビッツァ氏 外務大臣表彰(企業活動を通じた日本文化・知的資産の普及および両国の友好親善) |
| サ | 2018 | オットー・サラビア氏 在外公館長表彰(折り紙専門家、日本文化普及に貢献) |
| シ | 2019 | CIRMA在外公館長表彰(メソ・アメリカ地域研究所、 日グアテマラ両国間の相互理解や友好親善に寄与) |
| ス | 2020 | 兒嶋英雄氏 旭日単光章(当国における染色技術普及) |
| セ | 2020 | パブロ・ブエナフェ氏在外公館長表彰(合気道・残心道場創立者、日本文化普及に貢献) |
| ソ | 2020 | 中村誠一氏 外務大臣表彰(金沢大学教授、日グアテマラ両国間の相互理解や友好親善に寄与) |
| タ | 2020 | CALUSAC 外務大臣表彰(サン・カルロス大学言語センター、日グアテマラ両国間の相互理解や友好親善に寄与) |
| チ | 2021 | オットー・サラビア氏 外務大臣表彰(折り紙専門家、日本文化普及に貢献) |
| ツ | 2021 | ヘラルド・アギーレ氏 外務大臣表彰(グアテマラ・オリンピック委員会会長、日グアテマラ両国間の相互理解や友好親善に寄与) |
| テ | 2021 | キラ・リスクティン・デ・アブレウ氏 旭日双光章(イシド-キラそろばんスクール代表、そろばんを通じた日本文化普及) |
| ト | 2021 | ロベルト・モレノ氏 外務大臣表彰(バジェ大学学長、日グアテマラ文化・学術交流に貢献) |
| ナ | 2021 | ダニーロ・シエカビッツァ氏 旭日小綬章(企業活動を通じた日本文化・知的資産の普及および両国の友好親善) |
| ニ | 2022 |
ネビル・サイモン・スタイルズ・ウッドウォード氏 在外公館長表彰(グアテマラ・オリンピック委員会国際関係局長、 スポーツを通じた日本とグアテマラとの相互理解及び友好親善) |
| ヌ | 2022 |
オスカル・マエダ氏 在外公館長表彰(グアテマラ・オリンピック委員会オリンピック担当、 スポーツを通じた日本とグアテマラとの相互理解及び友好親善) |
6.在留邦人
(1)在留邦人:2022年6月現在の当国在住の在留邦人は284名であり、そのうち126名が永住者である他は、大使館、JICA海外協力隊、JICA等の経済協力プロジェクト、日本企業等の長期滞在者となっている。
(2)日本人学校:グアテマラ日本人学校は1977年(昭和52年)に設置された。2021年(令和3年)3月末に閉校。